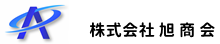タイヤ・ホイール(その2)
Tires and Wheels
スチールホイール
鉄鋼を用いて製造されたホイール、 比較的安価に製造できるので商用車や低価格車に多く採用される。
アルミホイール
アルミ合金を用いて製造されたホイール、アルミはスチールより軽量なので 燃費の向上とハンドリングの向上が期待できるが、一般に使用されている鋳造品 (溶かしたアルミを型に流し込み成型する方法。コストも抑えられ、量産するのに向いている。 しかし、強度を出すことができないので肉厚になり重量は 重くなる。)では余り差は無い。 鍛造品(高圧プレスにより成型する方法。プレスすることにより高強度になるので肉薄にできる。) は、軽量にできるが製造にコストがかかるので高価になり、市販車での採用は少ない。 スチールホイールとの比較では腐食しにくい点や、アルミニウムの熱伝導性の高さ・熱容量から、 ブレーキの排熱(放熱)を効果的に行えるメリットもある。 同時に、アルミホイールには車の外観をスタイリッシュにみせるという重要な役目もある。
マグネシウムホイール
マグネシウム合金を用いて製造されたホイール、 アルミニウムよりも軽量であり、アルミホイール以上に走行性能、燃費性能の向上が期待できる。 しかし、量産が効きにくく高価であり、またサイズが限定されているという汎用性の少なさから、 あまり一般的ではない。また、素材の特性として、塩分や 腐食や衝撃にかなり弱い点が挙げられる。 耐衝撃性や耐久性が低く、路面などとの接触で発火する危険性があることなどから市販車の採用はほとんどない。
各部名称
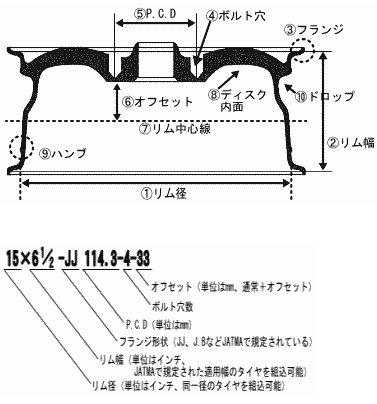
①リム径 同一径のタイヤを組み込む
②リム幅 規定適用幅のタイヤを組み込む
③フランジ タイヤと接合する耳の形状。
J(リム面からフランジ頭頂部の高さが17.5mm、フランジの厚さが13mm)
JJ(リム面からフランジ頭頂部の高さが18mm、フランジの厚さが13mm)のいずれかが一般的
④ボルト穴 車両に取り付けるボルトの入る穴。穴径・穴数(4~6穴が一般)に種類がある
⑤P.C.D ボルト穴の中心線を結んで描かれる円の直径をmmで表す
⑥インセット(オフセット)リム幅の中心線とホイール取り付け面との距離を表しています。
ホイールの取り付け面が中心線よりも外側であれば「インセット」。中心線よりも内側であれば「アウトセット」。
中心線上であれば「ゼロセット」。単位は「mm」となります。
(2008年7月11日より、「オフセット」の名称が変更されました 。これまでのプラスオフセットは「インセット」、
ゼロオフセットは「ゼロセット」、マイナスオフセットは「アウトセット」と3つの名称になりました。)
⑦リム中心線 リム幅の中心線。ゼロセット位置
⑧ディスク内面 規格は無いが、内面の形状によっては、
ブレーキキャリパーなどとの干渉により車両に装着できない場合がある。
⑨ハンプ タイヤが接するビードシート部からタイヤが内側に落ち込ま無いようにするための突起
【出典】https://fseibi.jp/document/wheel/
基本構造

アルミホイールは構造によって「1ピース」「2ピース」「3ピース」と3種類存在し、それぞれに特徴を持っています。
【1ピース】
1ピース構造とはリム(輪)部分とディスク(皿)部分が一体化している構造です。
そのため精度と剛性が高く、製造工程がシンプルなのでコストパフォーマンスに優れています。
剛性があるため、スポーツホイールとしてのシェアが多いのが特徴です。
【2ピース】
リム部分とディスク部分の2つの部品を繋いで一体化させる構造を2ピースと言います。
ディスク部分を単体で加工できるので、ミリ単位のインセット設定が出来ることと、
デザインの自由度が高いため、最近のアルミホイールの主流となっています。
ボルトがダミーの溶接タイプもあり、様々なバリエーションが楽しめるという特徴を持ちます。
【3ピース】
3ピース構造はリムを2つ、ディスクを1つ使って構成されるホイールで、
表面のリム(アウターリム)と裏側のリム(インナーリム)、ディスクの3つを固定して
組み立てる仕組みとなっています。北米や欧米でも最高級ランクに位置づけられているほど
クオリティの高いホイールでデザイン性に最も優れています。
【引用】https://www.goo-net.com/parts/parts-navi/tire-wheel/014.html
【出典】https://www.gs-maniac.com/wheel
タイヤチェーンのしくみ
近年では、スタッドレスタイヤを履いていても大雪時はチェーン装着が必須になる
「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の規制が発表さています。
雪道走行や凍結路での安全性はタイヤチェーンの方がグリップ力があり、
滑り止め効果が高く、勾配のきつい道や、新雪での走行は必須です。
形状により金属製・非金属製・布製などがありそれぞれ特徴があります。

【金属製】
昔からあるスタイルのもので、
金属製のチェーンをつないだもので、
はしごと型とリング型(亀甲型)がある。
はしご型は装着が簡単であるが、横滑りに弱い。
リング型は横滑りにも強いが装着が難しい。
金属製のメリットは剛性が高く、
雪道では抜群の安定性を誇り、価格も安い。
デメリットは乗り心地の悪化や騒音の大きさ、
雪道以外ではアスファルトを削ったり
チェーンが切れたりするため、
道路状況によりこまめに付け外しが必要になる。

【非金属製】
非金属製のタイヤチェーンは
主にゴムやウレタン製のものが多い。
金属製チェーンに比べ、軽量で錆びないこと、
車からタイヤを外さなくても付け外しができ、
振動や振動が少なく乗り心地が良いのが特徴。
雪道以外でもそのまま走行ができ、装着も簡単なことから、
最近では非金属チェーンが主流になりつつある。
非金属チェーンのデメリットは、金属製チェーンと比較すると
高価な点、折りたためないので持ち運びのときなど
収容スペースを大きく取ってしまう点が挙げられる。

【布製】
最近増えてきているタイプで、
布製カバーでタイヤ全体を覆って使用します。
軽くてコンパクトに収納でき、簡単手軽に装着でき、
振動や騒音がほとんどないのが特徴。
デメリットは、耐久性やグリップ性が多少劣ること。
また、チェーン規制が出ている道路では、
布製チェーンでは走行ができない場合が多いため、
あくまで緊急時用として考えたほうがよい。
【引用】http://www.yukidouraku.com/product/detail.html?id=1
http://www.yukidouraku.com/product/detail.html?id=6
http://reviews.f-tools.net/Car-Products/Autosock-Kouka.html
| タイヤのしくみ | ホイールのしくみ |